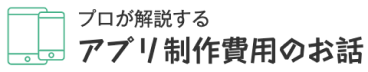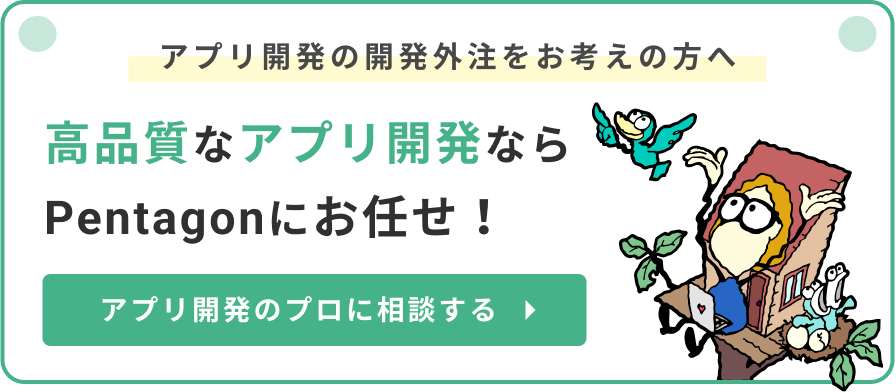アプリ開発の契約形態「準委任契約」とは?メリット・費用も解説

システムやアプリ開発で多い、外部への制作依頼。こうした外部と連携して進める開発では、発注側・受注側で結ぶ契約の種類によって担保する責任の範囲や業務内容も異なります。
今回はシステムの保守・運用の依頼に適した「準委任契約」をテーマに、概要やメリットなどをご紹介します。
アプリ開発の契約形態「準委任契約」とは?
アプリ開発を外部の制作会社などに業務委託する場合、業務委託契約を締結する必要があります。業務委託契約には複数の契約形態が存在し、今回ご紹介する「準委任契約」もそのなかのひとつです。
準委任契約は法律行為以外の業務を委託する契約形態で、法律行為(契約や遺言など)を行う場合は「委任契約」に該当します。アプリ開発における準委任契約は、アプリの完成を約束するのではなく、一定期間におけるエンジニアやプログラマの技術力や労働力の提供を約束する契約形態です。要件定義やメンテナンスなど、完成した成果物の納品を目的としない業務を委託する際に準委任契約が用いられます。
請負契約との違いは?
「請負契約」は仕事の完了に対して報酬が支払われる契約形態です。
請負契約はプログラム本体や各種設計書など、成果物を受託側企業が検収を済ませることで一つの仕事が完了し、基本的には検収が済むまでは報酬は発生しません。つまり、どれだけ技術力と労働力を仕事に費やしたとしても、目標とした成果物が完成しなければ報酬の請求ができないのです。
準委任契約と請負契約の主な違いは報酬がいつ発生するかという点です。請負契約で報酬が発生するのは先述のとおり仕事が完了したタイミングですが、準委任契約では一定の作業進捗状況に応じて報酬が発生します。そのため、準委任契約と請負契約の特徴や特性を理解して、開発モデルと相性が良い契約形態を選択することが大切です。
例えば準委任契約は善管注意義務・債務不履行責任という特徴が「アジャイル開発」と相性が良く、請負契約は仕事の完成を前提とする特徴から「ウォーターフォール型開発」と相性が良いとされています。
準委任契約を採用するメリットは?
準委任契約でエンジニアやプログラマを採用するメリットは、アプリ開発に必要な労働力を確保しやすいことです。アプリ開発業務においてシステム管理業務のみを委託したいケースでは、準委任契約で該当業務だけを委託する契約にすれば、エンジニアやプログラマを効率的に調達することが可能です。契約期間を詳細に取り決めることができるため、繁忙期など計画的に人材を確保する場合などに用いられます。また、正社員として採用する必要が無いため、社会保険など福利厚生にかかるコストや、教育コストがかからない点もメリットと言えるでしょう。
そして準委任契約は仕様変更に対する柔軟性もメリットです。一定期間を定めて業務遂行を委託する準委任契約では、期間内であれば業務指示を変更できます。請負契約では決められた期日までにアプリを完成させることを目標に契約を締結し、一度契約すると発注者は制作過程などに対する指示を出すことができなくなります。対して、準委任契約は業務の遂行における契約であり、アプリ開発で仕様変更が必要になっても柔軟に対応することが可能です。
準委任契約を採用するデメリットとは?
ここまでご説明してきた通り、準委任契約は仕事を完成させる義務が生じません。これより準委任契約にさまざまなメリットがある一方で、納期が明確に決まっているアプリ開発現場などではメリットが得られにくい契約形態と言えます。
アプリの設計やコーディングといった業務を委託するとき、決められた期日までに仕事を完了できなかったとしても受注側が責任を負うことは基本的にありません。準委任契約は、発注者側が委託した業務の成果に対して責任を負うことは必ず意識しなければならないのです。
また、準委任契約は業務遂行における成果が存在しないため、請負契約と比較すると契約の詳細が曖昧になる可能性があります。仮に曖昧な契約を締結してしまった場合、発注者側と受注者側で契約した業務範囲など認識の差が生じる可能性があるでしょう。準委任契約で業務遂行や報酬請求でトラブルを起こさないためには、曖昧な契約を結ばないことがとくに重要なのです。
準委任契約の費用感や報酬の形態
アプリ開発やIT業界では準委任契約は「システムエンジニアリング契約(SES)」とも呼ばれ、業務委託の一つとして広く普及しています。準委任契約の報奨は一般的なIT業界と同様に人月単価で計算され、月次あるいは数か月~年間単位で支払われる報酬形態です。
日本国内でアプリ開発業務をエンジニアやプログラマに委託する際の人月単価はおよそ100万円/月と言われますが、アプリの開発規模や開発期間などによって変動します。なお、2004年4月1日に施行された民法の改正では、準委任契約は「履行割合型」と「成果完成型」の2つに分けられています。
履行割合型
履行割合型は、委任事務の履行そのものの対価として報酬が支払われる委任契約です。
つまり、成果の有無にかかわらず、処理量に応じて報酬が支払われます。改正民法第648条第3項では、委任内容の履行不能となった場合・委任契約が途中で終了した場合には、受任者の帰責事由を問わず、既に行った履行の割合に応じて、受任者が委任者に報酬を請求できる旨が記されています。履行割合型では、履行状況が遅延したり、報告義務を怠ったりすると契約不適合責任と判定されるケースもあるため、委任側も受任側も認識しておきましょう。
成果完成型
成果完成型は成果物の納品までを約束する委任契約です。あくまで成果物の納品までを確約するものであり、完成物の質やその後の結果に責任はもちません。追加の機能開発や修正が発生するシステム開発などで多く用いられます。
準委任契約は高い・安い?
アプリ開発における費用は、開発内容と期間・人件費によって決まるため、契約形態によって金額の高低が決まるわけではありません。しかし、準委任契約では基本的に稼働したリソース分だけの報酬を支払えば良いため、無駄が減って余分なコストを生みにくい特徴があります。
例えば、一括請負契約は、事前に取り決めた通りの成果物を納品することを目的とした契約方式です。そのため、契約後にエンジニアなど受任側のスキルが足りていなかったとしても、契約をすぐに打ち切ることが難しいケースも発生するでしょう。一方、準委任契約ではそうしたコストリスクがないほか、途中の仕様変更に対応してもらうことも可能です。一括請負契約では、最初に定義した内容に沿った開発を行う契約であるため、こうした仕様変更に対応する柔軟性はありません。
このように、準委任契約と一括請負型のような他の契約方式では、仕様変更への対応可否・追加コストの発生リスク・完成責任・瑕疵担保責任などの観点でメリット・デメリットがあります。自社の状況に一番合う形態はどういった契約方式なのか、よく吟味してみましょう。
準委任契約をおこなう際に注意すべきポイントとは
準委任契約で気を付けるポイントは大きく2点、開発方式との相性と契約内容の変更に伴う条項の変化です。
一般的にアプリなどを含むITサービスの開発手法は、ウォーターフォール開発とアジャイル開発に分かれます。ウォーターフォール開発は開発手順を一つずつ確認しながら、フェーズ毎に全ての作業を遂行していく開発方式のことです。一方、アジャイル型は機能毎に開発・リリースを行う開発手法です。
前述のとおり、準委任契約は善管注意義務・債務不履行責任という特性をもつため、小規模開発を繰り返し行うアジャイル開発との相性が良くなる傾向にあります。このように、採用する開発モデルによってマッチする契約も異なるため、双方の相性をよく考慮しましょう。
そして、次に気を付けたい点が契約内容の変更に伴う条項の変化です。準委任契約では、民法で定められた「任意規定」があるものの、「契約当事者の意思表示」の方が優先されます。そのため、プロジェクトの内容に沿って契約書を作成すると、自社に不利なように働いてしまうケースもあります。そのため契約形態ごとに異なる任意規定を理解し、そのうえで契約内容をチェックすることが大切です。
まとめ
今回は契約形態の側面から、アプリ開発におけるポイントなどをご紹介しました。
準委任契約はリソースを確保しやすく、コストの無駄を生みにくい契約形態です。ケースバイケースではありますが、他の契約形態と比べると柔軟性のある形態だといえるでしょう。ぜひ自社にあった契約を結んで、スムーズなアプリ開発を叶えましょう。