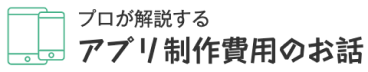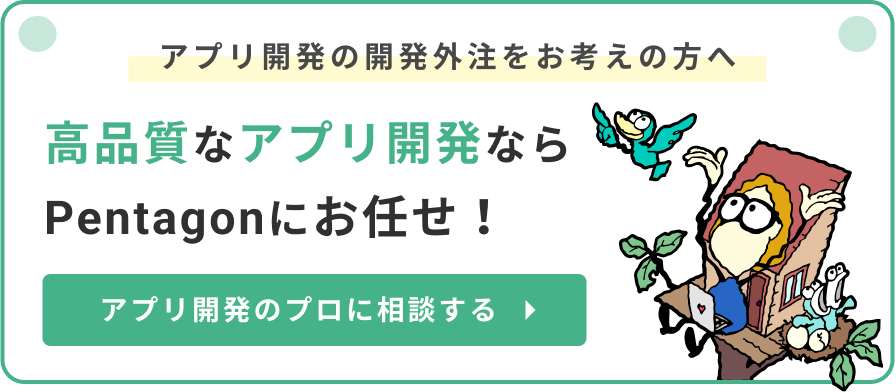【アプリ開発費用】契約形態ごとの違いとは|請負契約・準委任契約
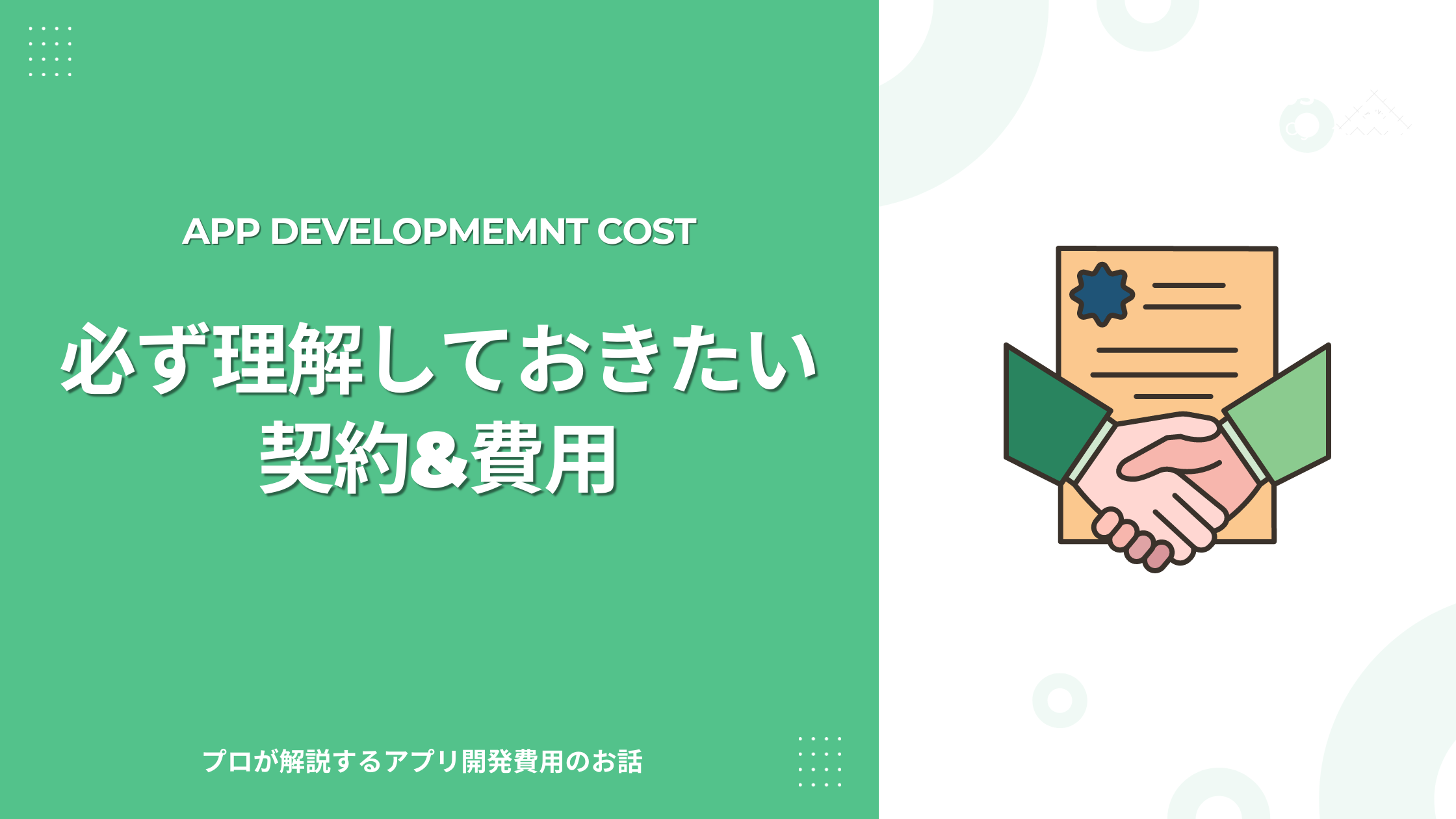
アプリ開発を委託する際には、依頼者と受注者である開発会社の間で複数の契約書が交わされます。アプリ開発に関する契約を交わす際には、成果物に報酬を支払う請負契約か、作業に対して支払いをする準委任契約のいずれかが用いられるケースが一般的です。
この記事では、アプリ開発における請負契約と準委任契約の違いと、各契約形態のメリット・デメリットを解説します。契約形態による依頼費用の違いも合わせて解説するので、ぜひ参考にしてください。
アプリ開発における契約形態の違いとは?

アプリ開発を委託する際には、対象とする業務内容や達成条件などに応じて、請負契約と準委任契約のいずれかの様式に沿って契約を行うことがほとんどです。
契約形態に応じて開発会社に課される義務や報酬を支払う条件などは異なります。取引先とのトラブルを防ぐには、契約形態ごとの特徴や使い分け方を理解しておくことがポイントです。まずは、請負契約と準委任契約の基本的な特徴、違いについて解説します。
請負契約
請負契約とは、仕事を完了させることを条件として契約を締結し、発注・受注を行う契約形態です。アプリ開発の場合、依頼者の設定した要件に沿った書類やプログラムコードなどを納品することで、開発会社に報酬が支払われます。請負契約では期日までに仕事を完了させることが開発会社に対して義務付けられ、進め方は開発会社が決められるほか、受注した仕事を下請け企業へ再委託することも可能です。
もしも期日までに納品が行われなかった場合、契約内容にもよりますが、開発会社が遅延損害金を支払うよう定められているケースが多いです。
請負契約の手続きをスムーズに進めるには、納期や支払い条件を明確に定めておきましょう。
なお、請負契約を締結する際には、開発会社は制作物に対して契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)を負う必要があります。これはアプリがあらかじめ合意した仕様書のとおりに開発されていなかった場合に、依頼者が開発会社に対して瑕疵担保責任を適用できるという仕組みです。具体的には、瑕疵修補請求・報酬減額・損害賠償請求・契約解除といった対応を実施することができます。
ただし、瑕疵担保責任を適用しない、担保責任を負う期間を短縮する特約を当事者間で結ぶこともできます。特約を結んでいない場合、通常どおり瑕疵担保責任が適用されます。
2020年に実施された民法改正に伴って、瑕疵担保責任は「契約不適合責任」という呼称に変更されています。報酬の減額に関する規定が一部変更されており、改正後は「依頼者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買い主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる」と民法第563条で定められています。
準委任契約
準委任契約は、依頼内容に沿って仕事を行うことを目的として締結されるものです。法律関連の業務では委任契約、その他の業務では準委任契約が締結されるという違いがあります。アプリ開発の場合、受注先の人材が持つ技術力や労働時間の提供を目的とする場合に準委任契約が用いられるケースが目立ちます。
準委任契約では、業務遂行へ向けて合理的に取り組むことが開発会社に対して義務付けられます。一方で、契約期間内に仕事や成果物が完成しなかった場合でも、契約条件を達成している場合は報酬が支払われる仕組みです。アプリの要件定義・保守管理など、完了や完成といった区切りがない業務を外注する場合には準委任契約が用いられます。
そんな準委任契約には、報酬の対象とする内容によって履行割合型と成果完成型の2種類があります。履行割合型は、履行された業務時間や作業量の割合に応じて報酬が発生するシステムです。業務を完了する前に契約期間が終了した、あるいは依頼者の責めに帰することができない事由によって労働に従事することができなくなった場合でも、開発会社はすでに履行した割合に応じて報酬を請求できます(民法第648条)。
成果完成型は、成果物を納品することで報酬が発生する契約です。成果完成型では仕事を完了させる義務は発生しませんが、業務を実施する上で一般的な水準の注意を払う義務があります(民法644条)。業務を完了する前に契約が解除されたり、労働に従事できなくなったりした場合には、依頼者が受ける利益の割り当てに応じた報酬を請求できます(民法第634条)。
それぞれの契約形態をとるメリット・デメリット
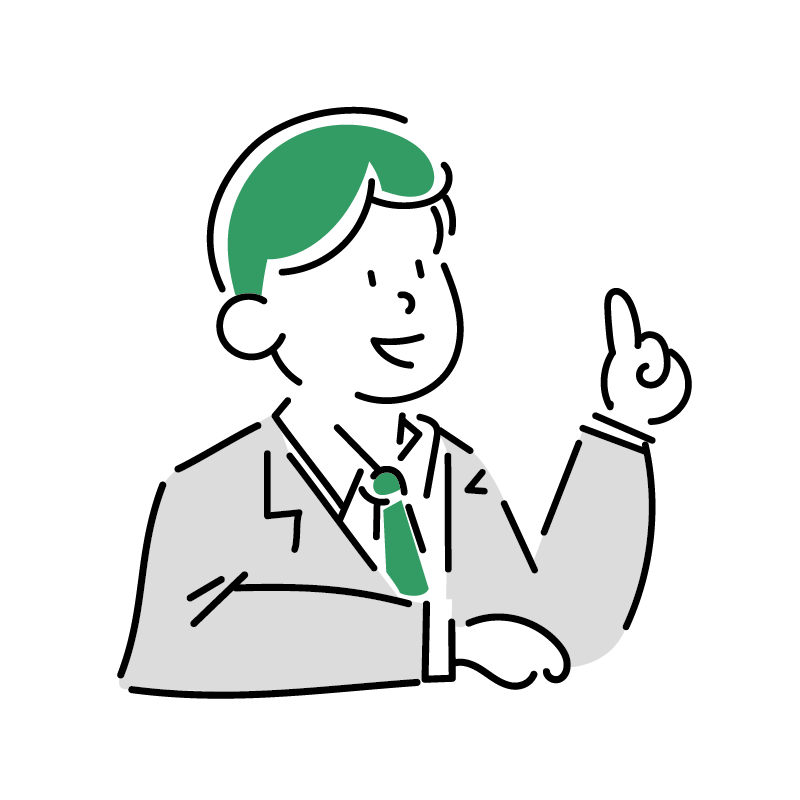
契約期間や依頼内容に関するトラブルを避けるためには、契約形態ごとの特徴やメリット・デメリットを適切に把握することがポイントです。ここでは、アプリ開発を依頼する際に請負契約、準委任契約を選択することのメリット・デメリットを個別に解説します。
請負契約のメリット
請負契約を締結する際には、納期や予算、必要条件を依頼者側で細かく指定できます。納品された成果物に不具合や品質不良が認められる場合、依頼者は開発会社に対して契約不適合責任の規定に沿って修正を求めることができる点も請負契約を活用するメリットです。
アプリ開発を全て外注する、もしくは自社内で対応できない工程を外部の専門家へ依頼したいといったケースにおいては、請負契約を締結することで目的を達成しやすくなります。完了した仕事や成果物に報酬を支払う請負契約では、費用に見合った成果物を獲得しやすいでしょう。
アプリの仕様や予算、納期といった情報を事前に共有することは前提になりますが、契約が成立した後は作業完了までを開発会社側へ委託できることが請負契約の特徴です。エンジニアの雇用や教育、アプリ制作や保守・管理などにかかる工数を節約できるので、自社の従業員にかかる負担を軽減できるでしょう。
また、請負契約の場合、アプリ開発に必要となる人材や設備は開発会社側が用意することがほとんどです。何らかの理由で増員や開発期間の延長が必要になった場合でも、追加費用は開発会社側の負担になります。依頼者にとっては、請負契約を活用することで開発コスト削減、業務効率化といったメリットが見込めます。
請負契約のデメリット
請負契約の場合、後述の準委任契約に比べて制作会社側の責任が重くなります。そのため、制作会社側もトラブルを未然に防ぐため、開発にかかる期間を長めに見積もるなど、バッファーを取る必要があります。その結果、開発にかかる必要が高くなりやすいというデメリットがあります。
また、開発会社側に業務を委託するので、自社の人材育成が滞るというデメリットがあります。アプリ開発の場合、請負契約を多用すると自社のアプリ開発スキルが向上しない、アプリ開発に関する経験や実績が蓄積されないことが主な問題点です。
そのほかにも、アプリの設計からリリースまでを外部企業へ依頼するため、自社内で改良や仕様変更などが行いにくい点も請負契約のデメリットだといえます。対策としては、事前に策定する「要件定義書」で両社の認識を細かくすり合わせておくことで、あとから要件が変更する可能性を減らしておくことが挙げられます。他にも、アプリの保守・管理も含めた請負契約を行うことや、自社内でアプリ開発に対応できる人材を雇用・育成することも有効です。
受注先に業務を委託する請負契約では、アプリの品質や開発速度は受注先の開発会社によって大きく左右されます。アプリ制作に必要なスキルを持っていない会社と請負契約を締結した場合、納品されるアプリの品質が低い、スケジュール通りに納品されないといった問題が発生するかもしれません。開発会社側の都合によって納品や修理を行うことが困難である場合、賠償請求や契約解除といった対応が必要になる場合も考えられます。
準委任契約のメリット
準委任契約の場合、契約期間や業務の進め方を細かく指定しやすいというメリットがあります。
例えばプログラミングや設計などを部分的に外注する際には、準委任契約を用いることで効率的に人材を確保することが可能です。プログラマーやエンジニアを特定の時期に増員する、自社内で対応できない業務を外注する際には準委任契約が適している契約形態と言えるでしょう。
また、準委任契約では労働力・労働時間を提供することを契約条件にできる点も、依頼者側にとってはメリットになる要素です。アプリの機能追加やバージョンアップ対応などが必要になった場合、準委任契約であれば依頼内容や契約期間の変更、延長を行いやすくなります。請負契約と比較して、依頼内容を柔軟に変更できるため、依頼者にとってはメリットになるのです。
そして、準委任契約は業務の遂行に対して契約を結ぶものであるため、開発途中の仕様変更などにも柔軟に対応できるというメリットがあります。
ここまでご紹介したことから分かるよう、制作予算や仕様変更に関するルールを依頼者側が指定しやすいことが、準委任契約を選ぶメリットのひとつです。
準委任契約のデメリット
準委任契約を締結する際には、依頼内容や報酬の発生条件が曖昧になりやすい問題があります。
労働力を提供することを報酬の発生条件にした場合、業務をどの程度の早さで進める必要があるか、契約期間の延長や短縮は発生するかなど、明確に決めておくことがトラブルを防ぐポイントです。なぜなら、契約条件を明確に定めていないと、業務効率の低下や報酬に関するトラブルが発生するリスクがあるからです。
準委任契約では開発会社側が仕事や成果物を完成させる義務は発生しないので、契約内容によっては依頼者側が金銭的なリスクを被ることがあります。成果完成型の準委任契約を締結した場合でも、開発会社が契約期間内に仕事を完了させる義務は発生しないので注意が必要です。
また、工数の増加によって開発期間が延長された場合、準委任契約では依頼者側の費用負担が増大してしまうというデメリットもあります。
各契約形態で費用の相場に違いはある?
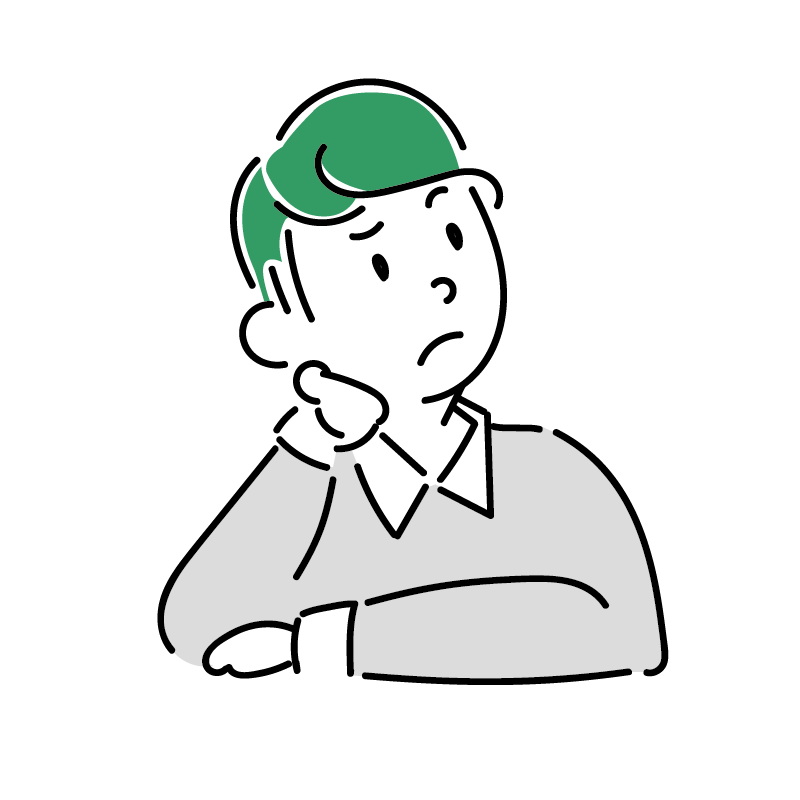
アプリ開発を同じ会社へ依頼する場合、請負契約の方が準委任契約と比較して相場価格が高くなると考えられます。請負契約では依頼者の要望に沿ったアプリを完成させることが開発会社に義務付けられるため、アプリ完成までにかかる期間や人件費が増大する傾向があります。
では、ここからは請負契約・準委任契約で相場価格に差が生じる理由と、契約を締結する際の流れを詳しく解説します。
請負契約を締結する際には、依頼内容・納期・報酬金額を明確化してから契約を締結します。基本的に報酬金額は固定であり、仕事や成果物が完成するまでの費用は開発会社側が負担するように規定されていることが請負契約の特徴です。実際に請負契約を締結する際には、制作期間が長期化することを見越して、見積もりを高めに設定するパターンがあるようです。
準委任契約を締結する際には、依頼内容と報酬金額、支払い条件を明確化してから契約を締結します。開発会社は依頼内容の達成へ向けて努力する義務がありますが、契約期間内に依頼内容を達成する義務はないことが準委任契約の特徴です。もし制作期間が延長された場合、追加費用は依頼者が負担するように規定されていることも、開発会社による見積価格が下がる要因になっているといえます。
そして、準委任契約では、依頼内容が達成されていれば仕事が完了していなくても開発会社は報酬を請求できます。請負契約と比較して準委任契約での見積もり価格は低くなるケースが多いようです。
なお、アプリ開発を外注する際には、アプリのジャンルや搭載する機能、保守・管理の対応などによって相場価格は異なります。開発費用の削減を目的とする場合、契約形態と合わせて確認することをおすすめします。
まとめ
請負契約は仕事を完了させることが条件になっており、準委任契約は依頼内容に沿って仕事を行うことを条件として締結する契約です。アプリ開発を外注する際には、設計やプログラミングなどの成果物がある業務は請負契約、要件定義や保守管理などの業務は準委任契約を選択した方がトラブルを防ぎやすくなります。依頼内容に沿った契約形態を選択することが、アプリ開発の外注をスムーズに進めるポイントです。