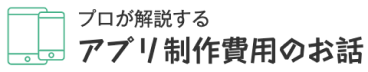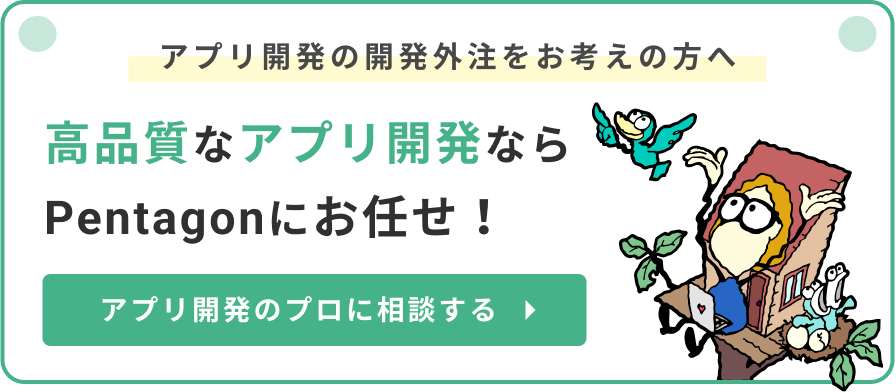アプリの保守運用にかかる費用とは?各項目の内訳や注意点を解説

スマホの普及にともない、近年は多くの企業がアプリサービスを開発、ローンチしています。しかし、アプリは作って終わりのサービスではなく、開発後の保守運用が非常に重要です。
ある調査によると、アプリのアクティブユーザー率は半年・一年・二年とどんどん減少していきます。また、インストール後30日以内のアプリのアンインストール率は50%を超過しているという報告結果も出ているようです。
その中でコンスタントに収益を出していくためには、ユーザーの意見を取り入れて常に改善を図ることは欠かせません。特に無料アプリ(フリーミアム)の場合、継続していく中でユーザーの課金を促したり、月額サブスクリプション型で継続利用してもらうためにリテンションレートを維持したりすることが非常に重要です。
こうしたユーザーのLTV、ひいてはサービスの売上に直結するのが保守運用のフェーズなのです。そこで今回は、アプリの運用保守にかかる費用について詳しくご紹介します。これからアプリ開発を検討している方はもちろん、目下開発中の方、現在運用中の方もぜひご覧ください。
アプリの「保守運用」とは?

アプリの「保守運用」とはアプリを開発・リリースした後に行う、運用やユーザーへのサポートなどのことです。
「保守」とは、機能の改善やシステムの一部に修正や変更を加えることを指し、「運用」とは、システムが正常に動作しているかを確認し、適切にサービス提供ができているかどうかを管理することを指します。
例えば、以下のような業務は保守・運用の範疇です。
保守:
・定期メンテナンス
・OSアップデートに伴う追加対応
・アプリケーション上のバグ対応
・使用時のトラブル対応
・機能の追加
運用:
・ハードウェアの故障対応
・ネットワーク障害対応/ネットワーク監視
・セキュリティアップデート/セキュリティートラブル対応
・データバックアップ/データ復旧
これらに費用が投じられず保守運用が充分に行われていないと、アプリが正しく機能せずユーザーにストレスや不信感を与えてしまいます。改善をせずそのまま放置した場合にはユーザーが離れていくだけでなく、会社や組織の信用を失うことに繋がる可能性すらあります。
しかし、保守運用に費用を使い、機能の改善やアップデートを重ねることでユーザーの満足度やアプリの認知度が高まれば、売り上げの上昇や会社・組織の知名度を上げる機会にもなります。
快適な状態でユーザーにアプリを利用してもらうためにも、アプリを開発した目標を達成するためにも、アプリの保守運用に必要な維持費を欠かせないステップなのです。
アプリの「保守運用」の具体的な項目

では、アプリの保守運用では具体的にどういったことをしているのか、するべきなのかをご紹介します。
アプリの「保守」に関する項目
まずは、アプリの「保守」に該当する項目についてご紹介します。
アプリのアップデート
アプリをリリースした後も、不具合への対応やユーザーから得られたフィードバックによる微調整などのアップデートが必要です。
アップデートをする際の費用は、アプリを一から全部作るスクラッチ開発と、そうでない場合で工数や金額が大きく変わります。さらに、自社開発か委託開発かによってもコストは変わるでしょう。
開発時点では外注開発を依頼していたり、システム保守サービスに加入していたりする場合でも、追加開発費が組み込まれていないケースは多々あるため、事前に確認しておくことが大切です。
OSアップデートへの対応
iOSやAndroidなどのOSは定期的にアップデートが行われます。今までは不具合なく利用できても、アップデートが行われた際に何らかの不具合が発生することで、アプリが正常に動作しなくなることもあります。そのときは、ユーザーに不便な思いをさせないよう、被害を抑えた適切な対応が必要です。この際に見つかった不具合の修正に必要な費用は「アップデート対応費用」と呼びます。
アプリの不具合の対応
バグや不具合の処理・対応も保守運用の大切な仕事です。アプリの利便性向上のためには、これらをスピーディーに対処する必要があります。トラブル解決の有無はサービスや提供元企業の信頼性に大きく影響するので、とても重要です。アプリの売上げやユーザーの数にも直結するため、維持費の中でもかなり重要視される項目です。
アプリへの機能の追加
ユーザーのニーズに合わせた機能の変更・改善を行います。1回や2回の機能変更・改善でユーザーのニーズを満たすことは困難なため、継続的に行うことが大切です。
一般的に、これらにかかる費用は「機能追加費用」と呼ばれます。あらかじめ追加開発を視野に入れた設計にして、機能追加の工数を減らすようにしておくと保守運用のコストを減らせるでしょう。
アプリの「運用」に関する項目
つづいて、アプリの「運用」に該当する項目についてご紹介します。
ハードウェアの運用
ハードウェアの運用には「ハードウェアの管理・故障対応」「ネットワーク障害の対応」「データの保持・バックアップ」「セキュリティシステムの維持・アップデート」「OSのアップデート」などの項目が含まれています。
システム自体を維持する他にも、それを支えるPCやサーバーといったハードウェアの管理やデータの保持といった業務もシステム保守運用の範囲です。故障やネットワーク障害が起きるとソフトウェアの正常な動作を妨げてしまい、バグなどを発生させてしまう可能性があります。こうしたトラブルを防ぐためにも、ハードウェアの保守運用は欠かせない業務なのです。
その他マーケティングなどを依頼する場合も
その他、保守運用には該当しないものの、アプリの認知度向上などを目的にさまざまなサービスを委託することがあります。
例えば宣伝のためのコンテンツマーケティングやSEO対策といったマーケティングに関する項目、ユーザーからの問い合わせに対応するヘルプデスクの運営などが該当します。
委託先の会社によって提供する内容が異なるので、自社の運営体制に合わせて検討・比較することをおすすめします。
保守運用にかかる費用の相場とは?
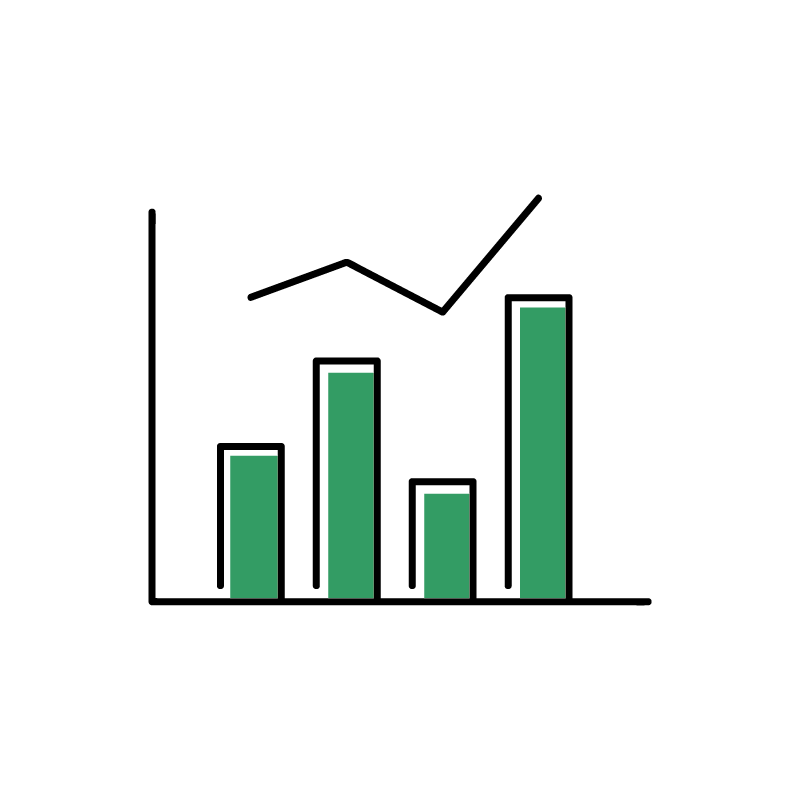
ここまでアプリサービスに重要な、保守運用について解説しました。
では、これら保守運用には一体どれほどの費用がかかるのでしょうか。シチュエーション毎に詳しくチェックしてみましょう。
保守作業にかかる費用
サーバーのレンタル費用や不具合修正などのアップデート費用、ドメインにかかる費用などの保守にかかる費用の一般的な相場は、年間あたり「アプリ開発費の15%程度」といわれています。
例えば、1,000万円かけて作ったアプリの保守費用は約150万円が目安です。
保守運用費用には、機能追加などに使う費用が含まれていないため、別途費用を確保する必要があります。
アップデート対応や機能追加の費用
追加する機能によって費用は大きく変動するため、今回はいくつか追加する機能の例をもとに、一般的な相場価格をご紹介します。
まず、ユーザーのメールアドレスから「ログインができる機能」を追加するのにかかる費用です。ログイン機能の実装はおよそ20~40万円となっています。一方、SNSなどの「アカウントと連携したログイン」を行う機能のみの追加であれば、若干コストを抑えることが可能で、およそ10〜25万円が相場です。なお、iOSアプリの場合「SNSアカウントを使ったログイン機能」を導入する際は「Sign in with Apple」も併せて導入する必要があるので、この分の開発費を加えるとコスト削減の効果はほぼなくなってしまうかもしれません。しかし、ログイン機能は他サービスにも開発部分を流用できるケースもあるため、自社の状況を鑑みて考えましょう。
次に、ショッピング系アプリで利用される「決済システム」です。既存のシステムを活用する場合と新規開発する場合によって異なりますが、およそ20~50万円が相場です。
その他、実店舗を持っている場合にも役立つ「Googleマップの搭載」にかかる費用は約10~20万円程、ゲームなどに実装されている「課金システム」の設置費用は10~20万円程です。ゲーム全体の調整や機能追加などを行うと合計で、300~1,000万円程度かかるケースもあります。
そして、デザインの変更については、外注した場合50~100万円程の費用がかかります。
このように、アップデートやアプリの機能追加に関わる費用だけでも、かなりの金額が必要になるのです。
運用作業にかかる費用
アプリが正常な状態を維持するための運用費は、監視を行う項目や、担保するべき品質によって費用が異なります。
例えば、24時間365日常に安定的に運用しなければならないのか、それとも毎月数時間はダウンタイムが発生しても良いのかでは、運用にかかる責任が変わります。その結果、運用費にも違いが出ます。
保守運用費用に関するポイント
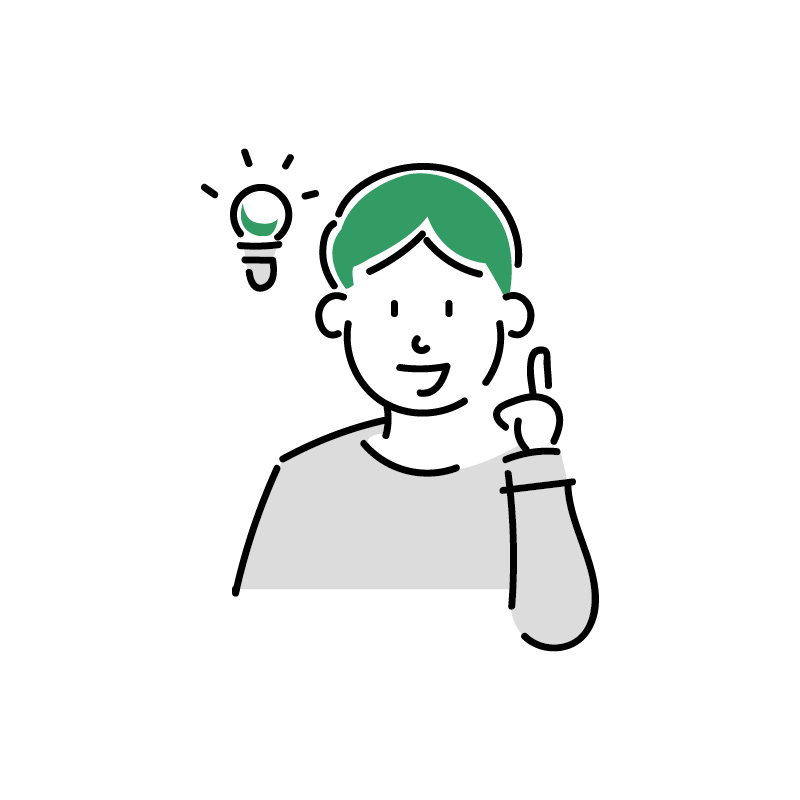
ここでは保守運用に関する、把握しておきたいポイントについて解説します。
対応するOS数が増えると保守運用費用も増える
アプリがiOSとAndroidの両方で開発している場合、開発言語が異なるので、それぞれに保守運用費用をかける必要があります。
また、iOSとAndroidアプリ両方とも、アプリストアへの登録料金がかかります。iOSアプリの場合は「Apple Developer Program」に開発者登録が必要で、年間およそ1万円(99米ドル)の登録料金がかかります。一方、Androidアプリの場合は、「Googleディベロッパーアカウント」の作成が必須で、およそ2,700円(25米ドル)の登録料金が必要です。
保守運用費用を抑えるためには?
保守運用にかかる費用を少しでも抑えるには、2つの手段があります。
まずは「依頼内容を少なくする」ことです。委託する部分と自社でカバーできる部分を明確化して、不要な依頼は避けることで費用を抑えられます。
特に、サイトの運営やマーケティング施策、ヘルプデスクの運営といったサービスの委託は、コストに大きく差が出てしまいます。こういった業務をできる限り自社で行うことで、コスト削減につなげられるのです。
次に挙げられるのが「フリーランス・副業のエンジニアに委託する」ことです。
フリーランス・副業エンジニアに委託することで、企業へ依頼するよりも安く依頼でき、維持費用をかなり削減できます。例えば月額で契約すると、いつでも安心してシステムを運用できるうえ、急なトラブルも迅速に対応できるメリットがあります。
また、安定したシステムの運用が可能であれば、フリーランスや副業のエンジニアに依頼することで「必要になったときだけ費用を支払う」といった形をとることも可能です。
しかし、フリーランスや副業の場合、1人で開発を担っているケースも多く、要件定義や担当範囲などその都度細かなコミュニケーションをする必要があります。また、クオリティーが保証されている訳でもありません。依頼する際には、これまでの実績や開発者のスキルセットをよく確認したうえで検討することをおすすめします。
委託先の保守運用のクオリティを確認しておこう
委託先の企業を選ぶには、業務のクオリティに信頼がおける会社・エンジニアであるかどうかが重要です。実績がまったくない企業だと、いざ委託するとなったときに細かい説明からしなくてはならず、コストに対して不安を抱いた結果、自社で管理したほうが早いという結論に辿り着きかねません。多くの開発会社はサイト上に実績などを掲載しているので、必ず確認するようにしましょう。特に自社のアプリと類似したようなサービス、業界での開発実績をもっている企業だとより安心です。
また、契約後も積極的にコミュニケーションをとることをおすすめします。常に認識の擦り合わせをして、互いの業務の範囲などを明確にしておくことで、バグやトラブル発生にともなう作業漏れなどを防げるでしょう。
定期的に費用や委託内容を見直そう
一定期間ごとに、システム保守運用費用を見直すことも大切です。
業務内容は、1ヶ月・2ヶ月・半年・1年といったように時間が経過するごとに変化します。そのため、一定期間ごとに費用を見直すことで余計なコストをカットできる可能性があります。
定期的にコミュニケーションをとることで、委託する必要がなくなった業務はないか、費用に対して業務は効率的に進んでいるかなど、費用対効果が大きいかどうかを判断する機会を得られます。コストカットの観点からも、1つの指針として、委託先との定期的なコミュニケーションは重要です。
まとめ
今回はアプリの保守運用に関する概要や費用相場、委託する際のポイントなどを解説しました。
ユーザーに末永く使ってもらうため、アプリの保守運用は欠かせないステップです。そして、保守運用といっても対応範囲は幅広く、利用ユーザーとのやりとりやサービスの改善、バグや機能の修正などその内容は多岐に渡ります。
せっかく長い期間と費用をかけて開発したアプリですから、アップデートや不具合の修正などの保守運用を繰り返し続けて、ユーザーが末永く、快適に利用できるアプリを目指しましょう。また、保守運用を委託する場合には今回の内容を参考に、充分な検討・比較をしてみてください。