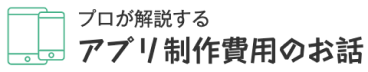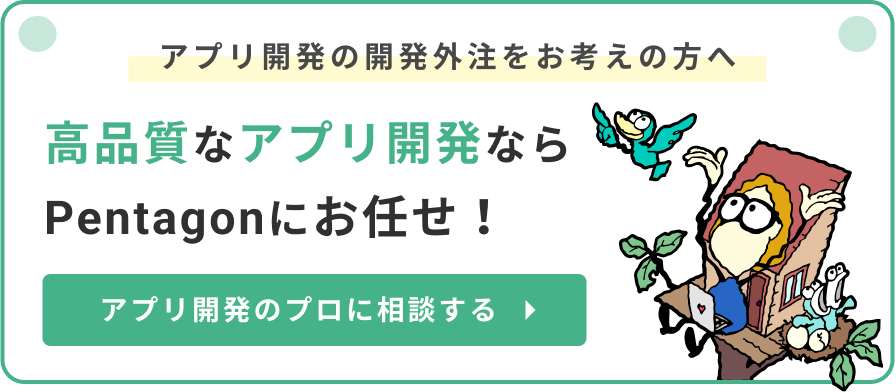アプリ開発の契約形態「請負契約」とは?メリット・費用も解説

近年ではアプリサービスを展開する企業も多く、上手く使うことでより大きなビジネスインパクトを生み出しています。すでにアプリをリリースした企業、現在アプリリリースを検討しているという企業も多いのではないでしょうか。
そんなスマホアプリですが、近年は開発費用が高騰したり、開発途中でプロジェクトが頓挫したりすることも少なくないようです。今回は、こうしたトラブルを生まないためにも、円滑なアプリ開発を進めるうえで欠かせない「契約形態」をテーマに解説します。
アプリ開発の契約形態のひとつ「請負契約」とは?
アプリ開発における「請負契約」とは、作業完了時に開発者側への報酬が発生する契約です。
つまりシステム完成までが契約内容となっていて、システムに欠陥が見つかった場合は、依頼者が契約解除や損害賠償請求を行う権利である「契約不適合責任」も発生します。
その際、依頼者には4つの解決策があります。目的物の不十分な部分を是正するよう求める「追完請求」や、追完請求をしても解決しない場合に代金の減額を求める「代金減額請求」、発注者に帰責事由がなく、受注側の帰責事由がある場合には「 損害賠償請求」「 契約解除」といった方法です。
システム開発を請負契約で依頼した場合は依頼者が契約後に指示を出すことは認められていません。例えば家を作る契約を結んだ場合、請負った人はキッチンから作っても、浴室から作っても構わないのです。ただし実際に仕事を進める個人が働く場所は問わないため、請負会社で働く場合もあれば、請負を委託した企業へ赴き働く場合もあります。さらに、契約書に再委託を禁止するという項目を入れている場合を除いて、受注した開発者側は別の会社やフリーランスへ下請けに出すことが可能です。
準委任契約との比較
準委任契約は、契約期間内に依頼された業務を行うことで報酬が支払われる、つまり作業時間に対して報酬が発生する契約形式です。こちらはシステムを完成させて納品するというよりも、業務の一部を手伝うようなイメージで、完成していなくても報酬が発生するため請負契約よりも業務遂行に焦点を当てた契約と言えます。
事務処理や一定の知識・スキルが求められる仕事など、さまざまな場面で準委任契約が結ばれています。
また、準委任契約では任意のタイミングで契約解除が可能である点が特徴です。ただしこれは契約内容によっても異なり、例えば「1年契約」期間の縛りを設けている場合は途中解約はできません。
さらに、準委任契約では契約不適合責任が発生しないほか、再委託も基本的に不可能です(契約内容によっては再委託が可能な場合もあります)。必要な時に必要な人材を確保できるうえに、仕様変更がしやすいので柔軟な対応ができるという点もメリットでしょう。つまり、準委任契約は「完成品や成果物の存在しない業務」や「事務の処理を目的とした業務」に向く契約形態だと言えます。
ちなみに委託契約との違いは、訴訟の代理など法律行為を扱う業務を弁護士事務所に依頼する業務など、法律行為であるか否かという点です。
請負契約を採用するメリットは?
請負契約をする際には予算や納期などの細かい指示を出すことができます。さらに民法541条では、開発者側にシステムを完成させる責任が発生することが記されています。
完成するまで報酬が支払われず未完成だったり、企業が要求するレベルを満たしていなかったりした場合は契約解除が可能なほか、納品後に不具合があった場合は「契約不適合責任」も発生するため、開発者側は開発期間や品質の確保といった計画を綿密に立てなければいけません。確実に求める物を入手したいのであれば、この請負契約が最適でしょう。
また、納品されてから報酬が発生するので、開発コストの把握・管理がしやすいというメリットもあります。
請負契約を採用するデメリットとは?
請負契約を採用した場合、完成後の修正が困難というデメリットがあります。
「契約通りの物を納品する」という仕組みになっている以上、契約内容に不備があった場合も修正ができないため、その結果依頼者側にとって不備のあるシステムが納品されるというトラブルが発生するケースもあります。依頼内容に不備がみられる際は、大きな問題やトラブルが発生することも多く、その際には納期までに間に合わせることが難しくなる可能性も高まるでしょう。こういった事故を防ぐためにも、契約する前に納品物の機能や仕様などの契約内容をよく確認しておくことが大切です。
アプリ開発を請負契約で依頼する場合の費用イメージ
請負契約の場合、費用は基本的に固定制です。完成後に報酬が発生する仕組みのため、依頼したアプリが納品されて検査などが終わったタイミングで報酬が確定することになります。一般的に、請負契約では開発期間の長期化を見込んで、見積り金額を高めに設定するケースが多いようです。もし万が一、納期に間に合わなかった場合は「遅延損害金」が発生するほか、納品されたシステムに欠陥や不具合が発覚すると「契約不適合責任」が発生します。
契約不適合責任は、民法の632条で「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」と規定されています。これは、依頼者はシステムの改修・修正、損害賠償、契約解除などを開発者側に請求できることを示すものです。2020年4月にこの法律が施行される以前は「瑕疵担保責任」という名称でした。法律変更後は、請求権が「納品物の納品から1年以内」から「契約不適合を知ってから1年以内」に変更されています。この法改正により「致命的なバグを発見したときには期間が過ぎていた」といったことがなくなり、依頼者側にとってはより安心できる内容となっています。
ちなみに、請負に関する契約書は「2号文書」と呼ばれる課税対象の書類のため注意が必要です。1万円以内は非課税となりますが、発注のために契約書を作成する際は収入印紙を貼って印紙税を支払う必要があります。こういった内容についても、契約を交わす際にはしっかり確認しておくと良いでしょう。
請負契約を交わす際に注意すべきポイントとは
注意すべきポイントとして「契約書の内容確認」が挙げられます。良くも悪くも「契約通りのもの」が納品されるため、以来の際は契約内容をよく考える必要があります。
また、納期や不具合発生時の対応や委託費用の支払方法、納品物の権利、検査方法、契約解除の条件などを明確にしておくと良いでしょう。機能や要件を明らかにした仕様書も契約書内に盛り込むと、依頼者側のイメージがより明確に伝わります。
さらに、契約書の内容が「プロジェクトの実態に沿って改変される」というケースも珍しくありません。請負契約には民法で定められた「任意規定」がありますが、それよりも「契約当事者の意思表示」が優先されます。つまり、システム開発会社が不利になる条項を一方的に変更している可能性もあるのです。発注側として不利益を被らないためにも、任意規定を理解したうえで、丁寧に契約書の内容をチェックしていくことが重要です。
まとめ
この記事では、アプリ開発の契約形態である「請負契約」の概要やメリット・デメリット、準委任契約との違いなどについて解説しました。
請負契約とは、作業完了時に報酬が発生する契約です。作業が完了することを前提としていて、納期が守られない場合には「遅延損害金」納品後の不具合や欠陥が見つかった際には「契約不適合責任」が発生します。
契約を交わす際には、任意規定を理解した上で、契約書の内容をよく確認するようにしましょう。